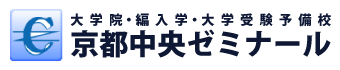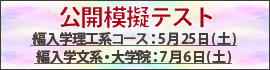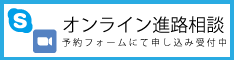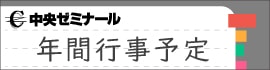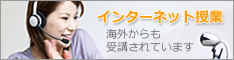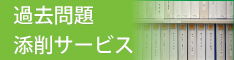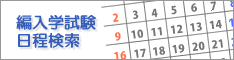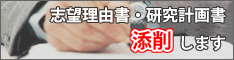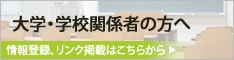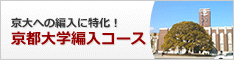傾向と対策
■同志社大学 文学部哲学科 3年次編入試験
英語
- ■全体の傾向
-
ここ最近の傾向としては、
- 英文和訳
- 文中のキーワードやキーセンテンスの解釈
- 哲学者や哲学史の知識
- ■英文和訳
-
哲学に関する英語の学術書を読みこなす能力が問われている。とはいっても、いたずらにむずかしい英文ではなく、関係詞やIt…that…構文、not~but~といった英文の構造を理解し、日本語訳に反映できれば、問題はない。普段から英文の個々のパーツがどのように組み合わさって一つの文を形成しているのかに注意して考えるくせを付けておくことが肝要である。
対策としては、
- 関係詞や構文など、英文の構造をしっかり把握できるようになること
- 哲学用語を英語でも読めるようになっておくこと
- ■文中のキーワードやキーセンテンスの解釈
-
解釈とは言っても、同志社の場合、解答者がそれぞれ独自の解釈を打ち出す必要はなく、問題文におけるキーワードやキーセンテンスのもっと具体的な意味を文中の言葉を用いて説明すればよい。英文のテキストを読んでそこで言われていることを把握する読解力が問われていると言えよう。対策としては、英文を訳すだけではなく、英文で言われている意味内容をも把握する訓練を普段からしておく必要がある。
- ■哲学者や哲学史の知識
-
哲学者や哲学史を問うものは大半が解答者の知識を問うものであり、英語の知識とは直接の関係はないものである。出題される哲学者も、2013年度のルソー(Rousseau)、2012年度のカント(Kant)、ハイデッガー(Heidegger)、ヴィトゲンシュタイン(Wittgenstein)、プラトン(Plato)、アリストテレス(Aristotle)、デカルト(Descartes)、スピノザ(Spinoza)、カルナップ(Carnap)、2011年度のトマス・アクィナス(Thomas Aquinas)、ロック(Locke)、バークリー(Berkeley)、ヒューム(Hume)、アウグスティヌス(Augustine)、ライプニッツ(Leibniz)、2013年度のフッサール(Husserl)、フロイト(Freud)、デリダ(Derrida)など、哲学史に登場するオーソドックスな哲学者が大半であり、哲学を学ぶ上で知っておくべき基本的な事柄が問われていると言えよう。
対策としては、
- 哲学史の知識を習得し、通常の哲学史で言われているところの主要な哲学者の主張を覚え、かつ哲学者間の関係を把握しておくこと
- 主要な哲学者の名前や主著名を日本語と英語との双方で覚えておくこと
ドイツ語
- ■全体の傾向と対策
-
ドイツ語の問題が、英語よりも受験者数が少ないためか、毎年は実施されていない。全体として言えることは
- 独文和訳
- 哲学者や哲学史に関する知識
- ■独文和訳
-
哲学に関するテクストをドイツ語で読む能力が問われている。対策としては、普段から以下のことに気をつけてドイツ語を学習する必要がある。
- nicht…sondern…といった構文やdie,der,dasをはじめとする関係代名詞、さらに英語にはない枠構造などに注意し、ドイツ語の構造を反映した日本語文をつくる。また、ドイツ語の文章は全体的に長くなる傾向にあるため、場合によっては適度に文章を区切って訳した場合の方が良いこともある。「次のような」「すなわち」といった言葉でつながりを示しつつ、文章を区切って訳す訓練をしておく必要がある。
- 主要な哲学者や哲学用語はドイツ語で何というのかを覚えておく。
- ■哲学者や哲学史に関する知識
-
受験者の知識を問うものであり、ドイツ語力とは直接の関係はないものが多い。扱われている哲学者も、2009年度のカント(Kant)、ヘーゲル(Hegel)、プラトン(Platon)、デカルト(Descartes)、2012年度のハイデッガー(Heidegger)、マルクス(Marx)、フッサール(Husserl)、サルトル(Sartre)など、哲学を学ぶ上で知っておくべき主要な哲学者が多い。対策としては哲学史の知識を吸収し、哲学史上の哲学者間の関係やそれぞれの流派について自分なりに表現できるようにしておくことが必要である。